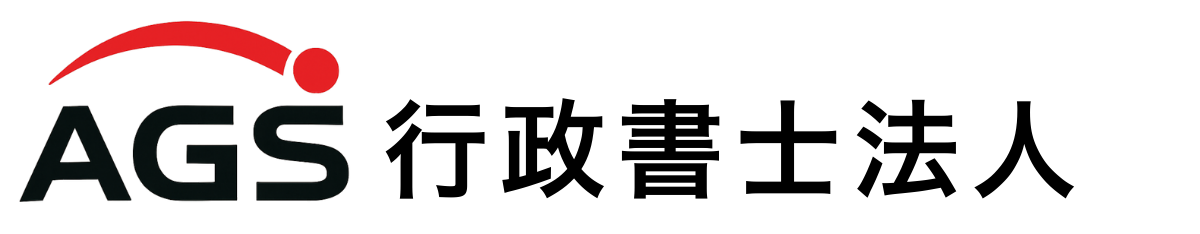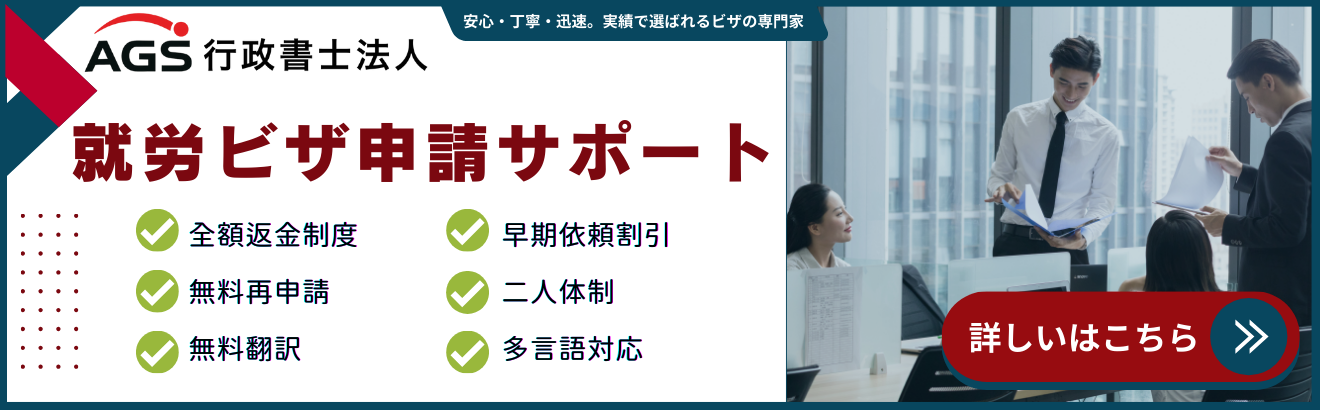技術・人文知識・国際業務ビザ申請の要件とポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの概要
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、平成26年入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格を一本化にしてできた在留資格です。しかし、技人国ビザに係る学歴又は実務要件と業務の関連性などは法改正前と同じく求められています。
これにより、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格を一本化にしたことは、在留資格該当性が認められる範囲の拡大により、例えば、同一社内に文系から理系職種に転換があった場合でも、在留資格変更手続が不要になりました。さらに、文系と理系の両方を含む学歴、実務経験や業務内容が判断対象となる場合に、関連性が認められやすくなりました。
- 「技術」に該当する活動とは、理学、工学そのほかの自然科学の分野に属する技術又は知識を有する業務とされています。
- 「人文知識」に該当する活動とは、法律学、経済学、社会学そのほかの人文科学の分野に属する知識を要する業務とされています。
- 「国際業務」に該当する活動とは、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とされています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件
技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件について、細かいところが多いですが、一般的に専門学校以上の学歴を要求されているが、10年以上の実務経験があれば学歴を問いません。
そして学校で勉強した専攻は実際の仕事内容と関連性がなければなりません。
就職の会社も審査対象となり、会社の規模が小さくて連続赤字の場合でもビザを取得しにくいです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査ポイント
中国の教育機関について
中国には、大学、成人教育、専科学校など様々な教育機関があります。「技術・人文知識・国際業務」の要件に認められる学歴は、大学院、大学、専科学校、短期職業大学、学位を与えることができる成人教育機関(学士学位証書が必要)を卒業して学位を取得した者です。
実務運用上は、大学を卒業しても学位を取得しければ不許可となるリスクが高い傾向となっています。
提出書類については、卒業証明書のみならず、学位証明書も求められています。
個人事務所に就職する場合
個人事務所であっても、日本で事務所等拠点があれば、「本邦の公私の機関」に該当しますが、実務運用上は、個人事務所の安定性、継続性、雇用必要性などの証明が会社と比べて困難で、不許可リスクが高くなります。
派遣契約の場合
派遣の場合、派遣元のみならず、派遣先も審査対象となっています。つまり、外国人本人、派遣元会社、派遣(就労)先会社の三つの審査があります。
派遣元の審査については、派遣事業に従事する必要な許認可が適正に取得するか、会社の安定性・継続性があるか等内容が問われます。派遣(就労)先会社の審査については、業務内容を技術・人文知識・国際業務ビザの要件に満たすかどうかが審査ポイントです。
なお、複数の派遣元と派遣契約を締結し、複数の派遣先会社に派遣されても、技術・人文知識・国際業務ビザを取ることが可能ですが、いずれの派遣先の業務内容が審査対象となり、申請要件に満たさなければなりません。
カメラマンの業務について
芸術系大学や専門学校で撮影技術を専攻して卒業した後、カメラマンとして技術・人文知識・国際業務ビザに変更申請する場合には、不許可となる例が多いです。実務上、結婚式場の業務は、単純労働であると判断される場合が多くて不許可リスクが高いですが、アニメや映画製作会社に撮影業務を従事する場合は、専門的な撮影技術を必要とする業務と認められ、許可を取得する可能性が高くなると思われます。
ホテルに就職する場合
大学や観光専門学校を卒業した後、観光地で外国人の利用が多いホテルで就職しようとして、技術・人文知識・国際業務ビザに変更申請する場合には、現時点実務上、許可しやすく傾向になっています。
フロントで接客業務は単純労働と見なされやすいですが、ホテルの規模、知名度、外国人利用数などは重要です。さらに、海外市場の拡大、海外客に対する様々なサービス、指導など業務に従事する必要な外国語の能力を持つことの証明も重要です。
実務上、観光地のリゾートや観光ホテルで許可を取得する成功率が高いですが、ビジネスホテルや規模小さい旅館などでは不許可リスクが高いです。
専門学校の卒業生の注意点
専門学校から卒業の留学生は、大卒等の場合と比べ、就職内容と学校で学んだ内容との関連性の審査がより厳しくなっています。したがって、専門士は就職の時より慎重に選択しなければなりません。一般的に、工業や商業を専修した場合は、関連性の証明が容易ですが、文化や芸術の場合は、関連性の証明が困難です。
在留期間の決定に関連する要素
実務上、雇用先の規模、申請人の学歴職歴、報酬額等が在留期間(1年、3年、5年)の決定に影響を与えます。申請人の能力、実績、人格など、又は雇用会社の規模、雇用必要性などをアピールできる証明書類があれば、例えば、日本語能力証明書、作品実績、採用理由書等入管法上の必要書類ではないですが、提出すべきです。

下記のボタンよりお気軽にお問合せください。